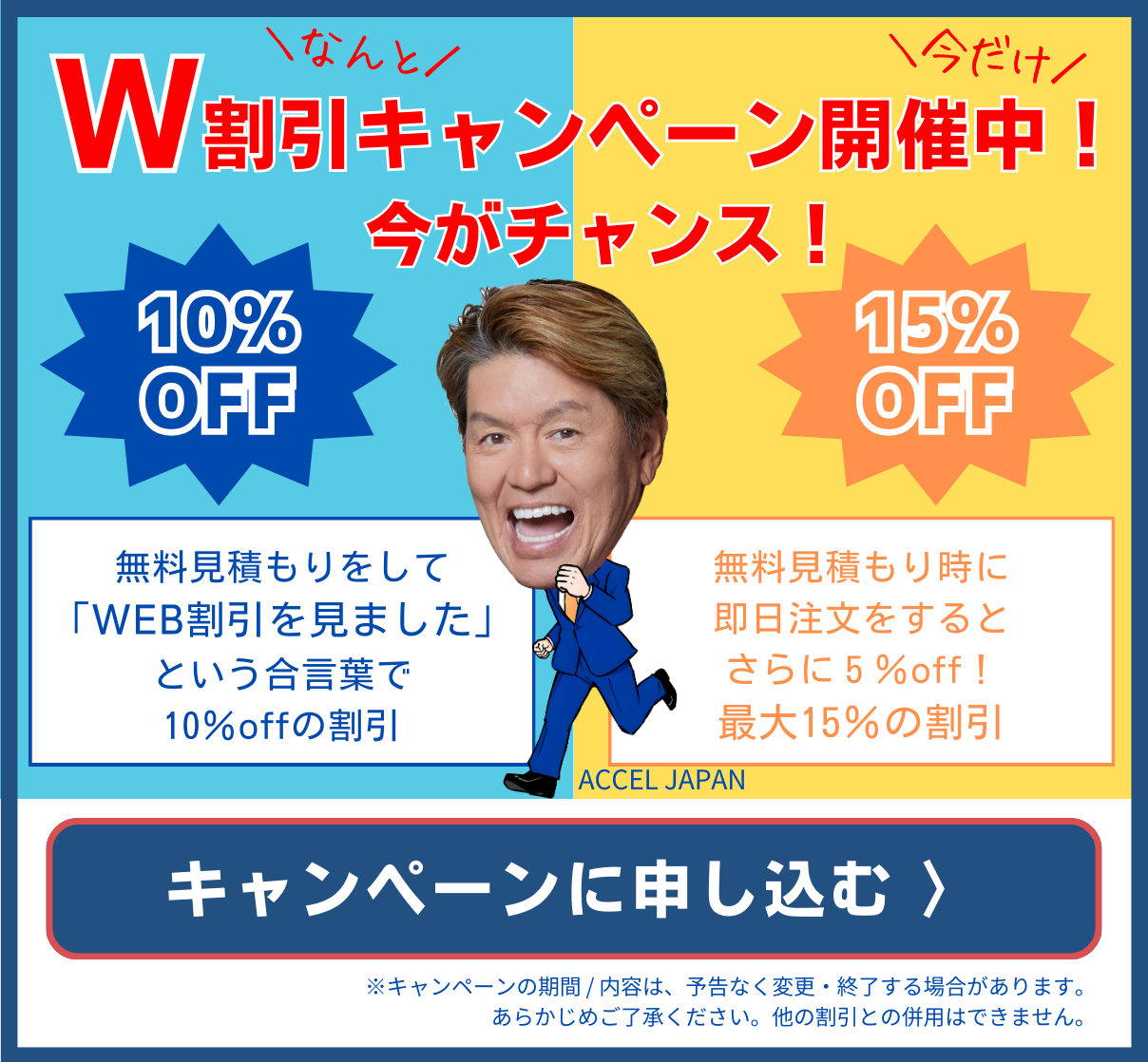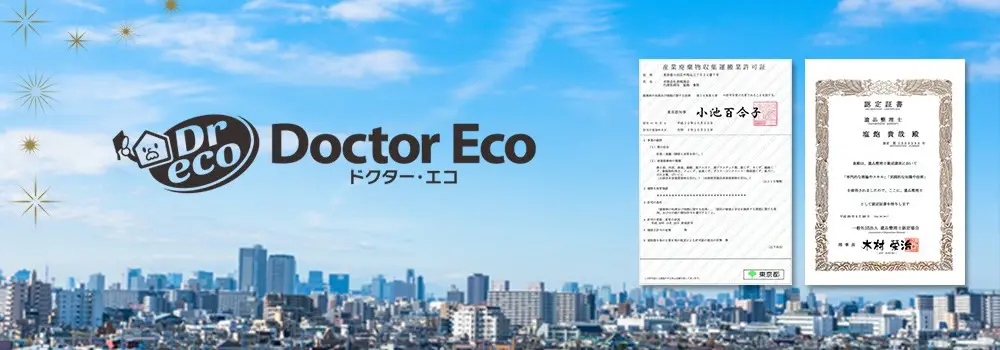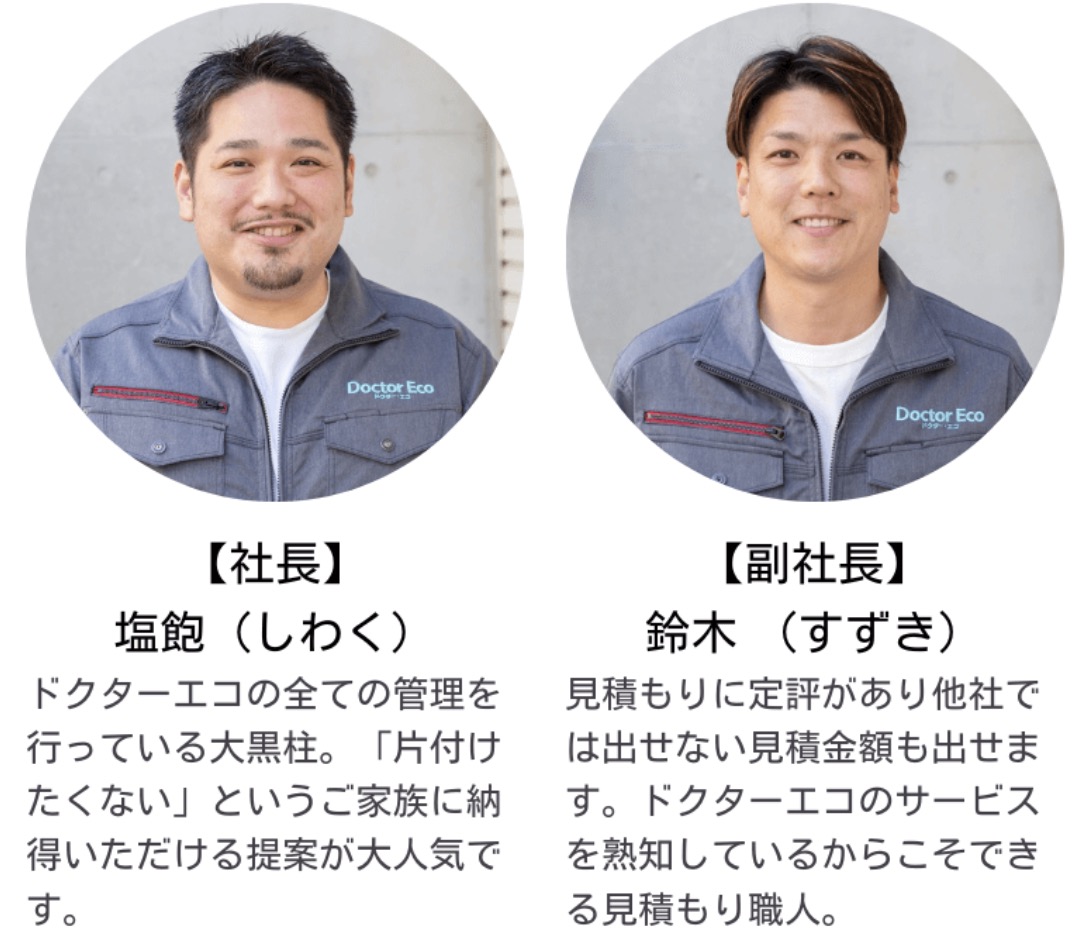「実家の親が亡くなり、家財道具がそのまま残っている」
「賃貸物件で入居者が夜逃げをして、荷物が放置されている」
……。
こうした「残置物(ざんちぶつ)」の処分費用は、一体誰が負担すべきなのでしょうか?
これまでは「とりあえずそのままにしておく」という選択も可能でしたが、2024年の「相続登記の義務化」や、改正された「空き家対策特別措置法」により、2026年現在は「放置すると、罰則金や増税で損をする時代」に突入しています。
この記事では、国土交通省のガイドラインや最新の法律に基づいた「費用負担のルール」と、損をしないための業者の選び方について、不用品回収のプロであるドクターエコが解説します。
【ケース別】残置物撤去費用は誰が払う?一覧表
残置物の処理責任は、物件の状況(賃貸・持ち家・売却時)によって異なります。
基本原則と、法改正によって注意すべきポイントをまとめました。
| ケース | 原則の 負担者 |
2026年時点の重要ポイント |
|---|---|---|
| 賃貸物件 | 借主 (入居者) ※連帯保証人・相続人 |
貸主が勝手に処分するのは違法です。ただし、契約時に国交省の「モデル契約条項」を結んでいれば、死後スムーズに処分可能です。 |
| 相続物件 (実家など) |
相続人 | 「相続登記の義務化」により、誰の所有か曖昧なまま放置できなくなりました。放置すると過料(罰金)のリスクがあります。 |
| 売却物件 | 売主 | 原則は「空」にして引き渡します。「残置物あり(現況渡し)」で売ることも可能ですが、撤去費用分以上の値引きを要求されることが一般的です。 |
| 競売物件 | 買受人 (落札者) |
前の所有者に請求権はありますが、回収不能なケースが大半です。撤去費用を見込んで入札する必要があります。 |
賃貸オーナー必見「モデル契約条項」による防衛策
特に賃貸物件において、単身高齢者の入居が増える中、万が一の際の「残置物処理」が大きな課題となっています。
これに対応するため、国土交通省と法務省は「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定しています。
モデル契約条項とは?
賃貸借契約を結ぶ際に、あらかじめ「入居者が亡くなった後、契約を解除し、残置物を処理する事務を誰に委任するか」を決めておく特約です。
これを利用することで、貸主(大家さん)は相続人を探す手間や、法的なリスクを減らしてスムーズに部屋を明け渡してもらうことが可能になります。
詳しくは、国土交通省の公式資料をご確認ください。
参考資料(国土交通省):
残置物の処理等に関するモデル契約条項の活用ガイドブック [PDF]
知っておくべき「法改正」のタイムラインと影響
残置物や空き家をめぐる法律は、ここ数年で劇的に厳格化されています。
「2020年の民法改正」から最新の「相続登記義務化」まで、所有者が押さえておくべきポイントを時系列で解説します。
① 【2020年4月施行】民法改正(敷金・原状回復ルールの明文化)
これまでは慣習で判断されていた「敷金の返還」や「原状回復」のルールが、法律の条文として明記されました。
これにより、賃貸契約における残置物撤去費用の負担についても、契約書(特約)での事前合意がより重要視されるようになりました。
- 敷金の定義:原則として返還しなければならない金銭と定義。
- 原状回復:経年劣化や通常損耗は、借主(入居者)が費用を負担する必要がないことが明確化。
参考資料(法務省):
2020年4月1日から民法(債権法)が改正されました [PDF]
② 【2023年4月施行】相続放棄後の「管理責任」の明確化
以前は相続放棄をしても「次の管理者が決まるまで管理義務が残る」とされ曖昧でしたが、改正により「現に占有している場合」に限定して「保存義務」を負うと明確化されました。
- 内容:実家に住んでいなかった子供が相続放棄をした場合、残置物の片付け義務を負わなくて済むケースが明確に。
- 注意点:鍵を持っている、貴重品を持ち出した等の行為があると「占有している」または「承認した」とみなされるリスクは継続します。
参考資料(法務省):
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の改正(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
③ 【2023年12月施行】改正空き家対策特別措置法
倒壊寸前の「特定空き家」だけでなく、管理不十分な「管理不全空き家」も行政指導の対象になりました。
- 内容:窓が割れている、雑草が繁茂している等の状態で、固定資産税の減免(住宅用地特例)が解除されるリスクが発生。
- 影響:残置物を放置しているだけで「管理不全」とみなされ、固定資産税が約6倍になる可能性があります。
参考資料(国土交通省):
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(概要) [PDF]
④ 【2024年4月施行】相続登記の義務化
不動産を相続してから3年以内に登記しないと、最大10万円の過料が科されることになりました。
- 影響:これまでは「誰も住まないし放置」できていた実家も、所有者を明確にする必要があります。
- トラブル:登記するには遺産分割協議が必要で、その過程で「誰が残置物を片付けるか」の押し付け合いトラブルが急増しています。
参考資料(法務省):
相続登記の申請義務化について
賃貸オーナー様への補足:
2021年に策定された「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を活用することで、孤独死などの万が一の際にスムーズに対応できます。
残置物の処理等に関するモデル契約条項の活用ガイドブック [PDF](国土交通省)
知っておくべき「3つの法改正」放置リスクの増大
「誰も住まないから、そのままにしておこう」。その考えは、今すぐ改める必要があります。
近年の法改正により、残置物のある空き家を所有し続けるリスクは劇的に高まりました。
① 相続登記の義務化(2024年4月〜)
不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請をしない場合、最大10万円以下の過料が科されることになりました。
登記をするには遺産分割協議が必要であり、その話し合いの中で「誰が家の片付け費用を出すか」というトラブルが急増しています。
② 改正空き家法の厳格化(管理不全空き家)
これまでは「倒壊の恐れがある(特定空き家)」場合のみ行政指導の対象でしたが、法改正により「管理が不十分な状態(管理不全空き家)」も対象になりました。
- 庭木が繁茂している
- 窓ガラスが割れている
- ゴミや残置物が散乱している
こうした状態で勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例(1/6への減税)が解除され、税金が約6倍に跳ね上がる可能性があります。
③ 相続放棄後の「管理責任」の明確化
「相続放棄をすれば、片付けなくていい」とは限りません。
民法改正により、放棄したとしても「現に占有している場合」は、次の管理者が決まるまで保存義務(管理責任)が残ることが明確化されました。
つまり、実家に住んでいたり、鍵を管理している状態で放棄しても、最低限の管理責任からは逃れられないケースがあります。 撤去費用の相場と「適正価格」の重要性
では、実際に業者に依頼した場合、費用はいくらかかるのでしょうか。
物価高騰や処分費の値上げ(インフレ)を反映した、2026年現在の目安相場は以下の通りです。
| 間取り | 費用目安(税込) |
|---|---|
| 1R・1K | 30,000円 〜 80,000円 |
| 1DK | 50,000円 〜 120,000円 |
| 1LDK | 70,000円 〜 200,000円 |
| 2DK | 90,000円 〜 250,000円 |
| 3LDK以上 | 170,000円 〜 |
なぜ、激安業者を選んではいけないのか?
ネット上には「積み放題1万円」といった格安広告もありますが、注意が必要です。
適正な処理を行うには、人件費・車両費・処分費(リサイクル費)が必ずかかります。異常に安い業者に依頼すると、以下のようなリスクがあります。
- 不法投棄:山林などに捨てられ、依頼主であるお客様が警察から連絡を受ける。
- 高額請求:荷物を積んだ後に、見積もりの数倍の金額を請求される。
- 貴重品の紛失:現金や権利書などを確認せず捨てられる(または盗まれる)。
ドクターエコの料金プランは、決して「業界最安値」ではありません。
しかし、「法令遵守」「日本人スタッフによる丁寧な作業」「貴重品の確実な返還」をお約束する、安心の適正価格です。
ドクターエコなら「貴重品探索」も標準サービス
残置物の中には、タンス預金(現金)や通帳、想い出の品が紛れていることが多々あります。
ドクターエコでは、単に捨てるのではなく、以下のサービスを標準(追加料金なし)で行っています。
- ① 貴重品の徹底探索・仕分け
本の間やタンスの裏まで、日本人スタッフが丁寧に確認します。 - ② 現金・貴金属の正直な返還
発見した現金等は、隠さず必ずご依頼主様へお渡しします。 - ③ 2人一組による相互監視
トラブルや不正を防ぐため、必ず複数名で作業にあたります。
残置物撤去に関するよくある質問
- Q. 相続放棄をしましたが、家の片付けは必要ですか?
- A. 状況によりますが、管理責任が残る場合があります。
民法改正により「現に占有している」場合は、次の管理者が決まるまで保存義務があります。空き家状態で放置して近隣に被害が出た場合、損害賠償を請求されるリスクもあるため、まずは専門家にご相談ください。 - Q. 賃貸物件で、夜逃げした入居者の荷物を勝手に捨ててもいいですか?
- A. 絶対にNGです(自力救済の禁止)。
勝手に処分すると、逆に損害賠償を請求される恐れがあります。まずは連帯保証人に連絡を取るか、法的な手続き(明け渡し訴訟等)が必要です。ドクターエコでは、弁護士と連携した対応のアドバイスも可能です。 - Q. 見積もりは無料ですか?追加料金はかかりますか?
- A. お見積もりは完全無料です。
現地調査を行い、確定したお見積もり金額以外に追加料金を請求することは一切ありません。「適正価格」で、安心・確実な作業をお約束します。