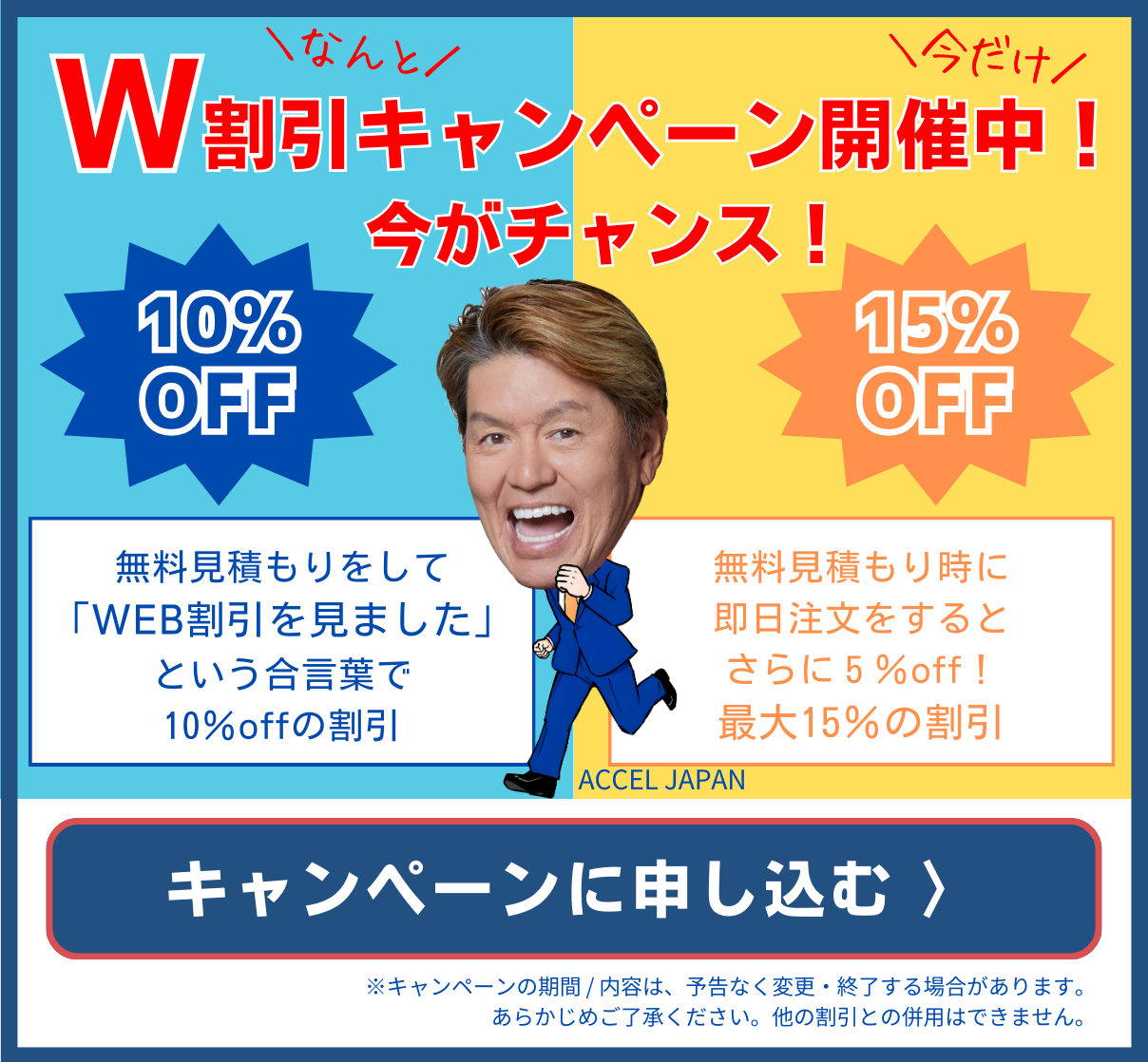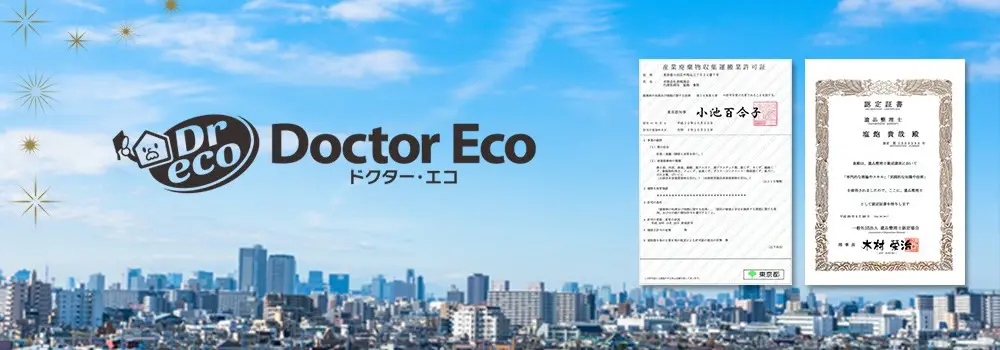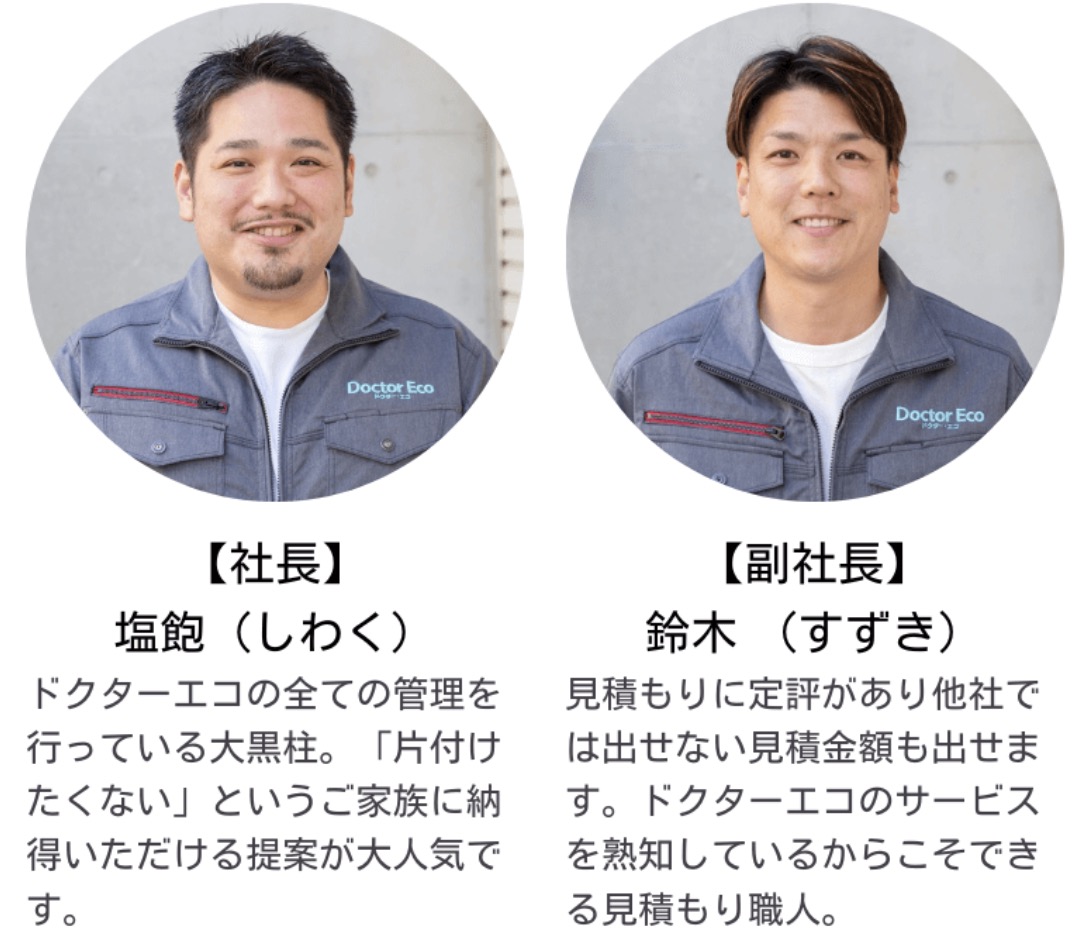毎年クリスマス翌日に廃棄されるケーキは少なくありません。まず“なぜ起きるか”を構造で捉え、家でも店でも実行できる対策に落とし込みます。
12月24日の夜、都内の大型スーパーでは値引きシールを貼るスタッフが慌ただしく動き回り、バックヤードには青い処分用カゴが静かに積まれ始めます。ショーケースにはまだケーキが並び、「今年も余りそうだな…」という店員の小さな声。
しかし一方で、家では「冷蔵庫のスペースが足りない」「食べきれずに翌朝しぼんだケーキをどうするか」と悩む家庭が増えています。このギャップこそ、クリスマスケーキの食品ロスが毎年繰り返される理由です。
この記事では、 「なぜ大量廃棄が起きるのか(利益構造)」と「どれだけ捨てられているのか(データ)」を押さえたうえで、家庭とお店の両方で今すぐできる対処・保存方法を、生活の動きがイメージできる形でまとめます。
なぜ、大量のクリスマスケーキが廃棄されるのか?
クリスマスケーキは、実質的な販売時間が12月24〜25日の約48時間しかない“超短期決戦”の商品です。この短い期間に売り逃しをすると、売上だけでなく評判・シェアも失うため、現場では「欠品するくらいなら、少し作り過ぎても仕方ない」という判断になりがちです。
完売にしてしまうと損をするという、クリスマスケーキ特有のビジネスの構造が、大量廃棄を生んでしまっています。どういうことなのか、詳しく説明していきます。
クリスマスケーキは、どのくらい捨てられている?
推定:クリスマス直後に廃棄されたケーキ等は約79トン(レンジ 34〜152トン)。 ホール換算で約16万個(500g/個想定)、一人分では約79万人分(100g/人想定)。 もし無駄にならずに届いていれば、中規模都市まるごと一夜のデザートをまかなえる規模。
※概算前提:ホール500g/個、1人分100g。季節菓子を含む推計。
廃棄量の換算(ホール個数・人数)
| 総量 | ホール個数(500g/個) | ホール個数(400g/個) | 人数換算(100g/人) |
|---|---|---|---|
| 34t | 約68,000個 | 約85,000個 | 約340,000人分 |
| 79t (中央値) |
約158,000個 | 約197,500個 | 約790,000人分 |
| 152t | 約304,000個 | 約380,000個 | 約1,520,000人分 |
※四捨五入の概算。ホール重量やカットサイズにより上下します。
換算の前提
- ホール重量の目安:4–5号=400–500g、6号=約700g
- 1人分カット:80–120g(中間値100gを使用)
- 総量は「クリスマス向け菓子を含む」推計。ケーキ単独の全国統計は未整備
クリスマス翌日の“家庭のリアル”
クリスマス翌朝の冷蔵庫では、こんな状況がよく起きています。
- ケーキ箱をそのまま入れて冷蔵庫のスペースを圧迫している
- ラップをせずに入れてクリームが乾燥し、しぼんでしまう
- ホールのまま残っていて誰もカットせず、手がつけられない
- 「もう飽きたからいいか」となり、結局夕方にまとめて廃棄されてしまう
特に5号(直径15cm)や6号(直径18cm)のホールケーキは、4人前後の家族でも持て余しやすく、家庭内の食品ロスの大きな要因になっています。
さらに、ケーキは時間が経つとイチゴから水分が出てクリームが崩れたり、スポンジが乾燥したり、暖房の効いた室内で傷みやすかったりと、品質劣化が早いデリケートな食品です。正しい保存と“食べ切れる量の選び方”ができていないと、せっかくのケーキが「翌日の負担」と「ゴミ」に変わってしまいます。
なぜお店は廃棄されるのに多く作るの?
結論:3個作って2個売れれば黒字になるケースが多いからです。利益を出すために「欠品(売り切れ)」より、少し過剰に作る方が利益を生みやすい構造が、こうしたクリスマスケーキの大量廃棄を招いています。
ケーキの売値P=5,000円/原価C=2,200円/“売り切れの評判ダメージ”g=800円
- 3個作るコスト:2,200×3=6,600円
- 2個売れた売上:5,000×2=10,000円
- 余り1個を捨てた場合の利益:10,000−6,600=+3,400円(黒字)
- 余り1個を半額で売れたら:10,000+2,500−6,600=+5,900円(さらに黒字)
要するに、1個捨てることになったとしても3個のクリスマスケーキを作ったほうが、利益を生むのです。
完売だとなぜ、損をするのか?
完売した場合、原料も全て残すことないので、利益を最大化できたと普通なら考えるかもしれません。 しかし、商戦となると話が少し変わってきます。
- 欠品の損=(売値−原価)+評判ダメージ=(5,000−2,200)+800=3,600円
- 作り過ぎの損(捨てる想定)=原価=2,200円
→ 「欠品の方が痛いので、在庫は“少し過剰”に寄りやすい。」というのが現状です。
半額販売できた場合でも利益になる
- 余った1個の売上(半額):2,500円
- その1個の原価:2,200円
- 差額:+300円(=2,500 − 2,200)
=余剰を値引きで売れればダメージはさらに小さく、欠品3,600円に比べて在庫は“少し過剰”を許容しやすくなります。
| 売り方 | 回収額 | 余剰1個の損益(= 回収 − 原価2,200) |
|---|---|---|
| 廃棄 | 0円 | −2,200円 |
| 30%引き | 3,500円 | +1,300円 |
| 50%引き(半額) | 2,500円 | +300円 |
| 70%引き | 1,500円 | −700円 |
※数値は例。実際は店舗の売価・原価で置き換えてください。
それ以外の原因3つ
- 需要集中:12/24〜25の超短期決戦(販売機会はほぼ48時間)。
- 衛生・表示:生菓子は消費期限が短く、翌日販売や寄付が難しい。
- サイズ誤差:5号・6号を人数に合わず購入→家庭で余らせやすい。
この問題は、クリスマスケーキだけに限った話ではありません。
節分の時期に話題になる恵方巻の大量廃棄も、 「当日しか売れない」「売れ残れば即廃棄」 という同じ前提条件のもとで発生しています。
実際、2026年の恵方巻では、 大量廃棄がSNSで話題にならなかった一方で、 売り切れが続出するなど、 作りすぎない方向へ設計が変わり始めた兆し も見られました。
恵方巻の大量廃棄とフードロスについては、 以下の記事で、現場視点から詳しく整理しています。
恵方巻の大量廃棄とフードロス|2026年、売れ残りが話題にならなかった理由
行政が進めるフードロス対策6つ
食品ロス削減推進法(2019施行)
国・自治体・事業者・消費者の役割を定め、普及啓発や計画づくりを制度化した土台の法律。
NO-FOODLOSS PROJECT(国民運動)
“ろすのん”で周知。食べきり・持ち帰り・食品寄附・てまえどり等の行動を広報し、教材やポスターも配布。
「てまえどり」公式資材(小売向け掲示物)
棚の手前の商品を選ぶ購買行動を促すポスター等を3省連名で無償配布。店舗掲示で行動変容を後押し。
食品ロス削減月間(10月)・食品ロス削減の日(10/30)
消費者庁・農水省・環境省が連携し、10月に集中的な啓発や事例紹介・ポスター展開を実施。
サプライチェーン実証(期限管理×動的値付け等)
賞味期限のデータ化やダイナミックプライシング等の実証で、在庫適正化と廃棄抑制を検証。
自治体の「30・10(さんまる・いちまる)運動」
乾杯後30分&お開き前10分は着席して食べきる――宴会の食べ残し削減を自治体が周知。年末年始など重点期間に展開。
企業ができる事前にクリスマスケーキ廃棄を減らす方法
需要側を賢く誘導
何人で食べるか、いつ食べるか、冷蔵庫の空きはあるかを確認し、号数だけに頼らずサイズ提案。受け取り日は23〜26日に分け、予約特典やハーフ・カップケーキで「買い過ぎ」を防ぎます。
供給側を見える化
予約を中心にして当日の製造は最小限に。店頭やアプリで在庫数を見せ、18:00→19:30→閉店前の段階的な値引きを定時実施。天気や来店数を見て仕込み量を小刻みに調整します。
保存&転用を標準化
会計時にQRで「小分け→二重包み→冷凍」「前日からの冷蔵解凍」を案内。翌朝に使える簡単アレンジ(トライフル・アイス重ね・フレンチ風)も配布し、家で食べ切れるようにします。
廃棄の適正化
食べられない分は水分を切り、紙で包んで指定袋へ。収集直前に出して臭い・液だれを防止。箱やフィルムは資源分別。事業者は食品リサイクル法の基準とマニフェストを徹底します。
私たちができる7つのフードロス対策
消費者が賢く選べば、販売側も在庫を適正化でき、ロス削減と利益の両立に近づきます。
0) まず予約する
予約なら「確実に買える・行列が短い・人数に合うサイズを選べる」。お店も需要を読みやすくなり、過剰製造が減ってロス削減に直結します。
1) サイズを決めてから買う
人数×1カット(目安100g)で必要量を先に計算。迷ったらハーフやカップで“食べ切り設計”。
2) 受け取り日を分散する
家族の予定に合わせて23〜26日に分けて受け取り。集中を避けるほど余りにくくなります。
3) 当日シェアを前提にする
親戚・友人・職場に取り分け前提で声かけ。小皿・ラップを多めに用意してスムーズに配る。
4) 余りは“5分冷凍”で救う
1カット→ラップ密着→袋で二重→平置き冷凍。果物は別容器。解凍は冷蔵で6〜8時間。
5) 翌朝アレンジで食べ切る
トライフル、アイス重ね、フレンチ風で楽しく消費。家族の好みで1つ決めておくとラク。
6) アレルギーと日付ラベル
小分け包みに日付・中身・アレルゲンをメモ。家族が間違えない工夫で安全に。
7) 正しく“捨てる”も大事
食べられない分は水切り→紙で包む→指定袋。箱やフィルムは資源分別。収集日は地域ルールに従う。
クリスマスケーキを翌日までおいしく食べ切る方法

クリスマスケーキは、生クリームやフルーツの水分で傷みやすく、暖房の効いた室内では特に劣化が早いデリケートな食品です。
食べ切る前提で「すぐ小分け・正しく保存」しておくことで、翌日までおいしく楽しみながら食品ロスも減らせます。
手順1:食べる量と余る量をざっくり決める
まずは家族の人数と「今すぐ食べる量」をざっくり決めます。
目安は1人あたり約100g(1カット)。
「今食べる分」と「翌日以降に回す分」をここで分けておくと、ダラダラ食べ続けず、無理のない量で楽しめます。
手順2:余る分はその場で小分けカットする
余りそうな分は、食後にまとめてではなく食べ始める前にカットしておきます。
1カットずつ平らな形になるよう切り分け、フルーツが多い部分と少ない部分をバランスよく分けると、解凍後も食べやすくなります。
手順3:1カットずつラップで密着&二重包み
カットしたケーキを1つずつラップでぴったり包み、空気が入らないよう密着させます。
そのうえで清潔な保存袋に入れて二重包みにすると、冷蔵庫や冷凍庫のニオイ移りを防げます。
イチゴなどくだものが多い部分は、別容器に分けて保存すると水分で崩れにくくなります。
手順4:冷蔵なら当日〜翌日、冷凍なら1〜2週間を目安に
冷蔵保存の場合は、当日〜翌日までに食べ切るのが基本です。
食べ切れない量は、思い切って冷凍保存に回しましょう。冷凍したケーキは、目安として1〜2週間程度で食べ切ると、風味の劣化が少なく済みます。
手順5:食べる前に冷蔵庫でゆっくり解凍する
冷凍ケーキを食べるときは、前日の夜に冷蔵庫へ移し、6〜8時間かけてゆっくり解凍します。
室温で一気に解凍すると、表面だけ温まり中が冷たいままになりやすく、食感も悪くなりがちです。
手順6:翌朝は“アレンジレシピ”で楽しく消費する
解凍したケーキは、そのまま食べるだけでなく
・グラスに重ねるトライフル風デザート
・アイスと重ねたパフェ風
・薄く切って卵液に浸したフレンチトースト風
などにアレンジすると、家族も飽きずに食べ切りやすくなります。
手順7:どうしても食べられない分は“正しく捨てる”
それでも食べ切れない分は、無理に残さず早めに処分します。
ケーキのクリームやフルーツは水分・油分が多く、袋の底抜けや臭いの原因になりやすいため、
1) 紙などで水分を軽く拭き取る → 2) 新聞紙などに包む → 3) 指定袋に入れる
という順番で捨てると安心です。箱やフィルムは、自治体のルールに従い資源ごみとして分別します。
年末年始に読みたい関連リンク
- 【2025–2026】東京23区の年末年始ごみ収集スケジュールと公式リンク集|燃えるごみ・資源・粗大ごみ
- クリスマスの不用品は“買取=割引” 現金化より総額が安くなる理由
- 東京でクリスマスの混雑を避けて回れるイルミネーションスポット【2025】
- 東京のクリスマスマーケットとイルミネーションを同時に楽しめるおすすめエリア5選【2025】
よくある質問
- Q. 予約は不必要?
- A. 不要ではありません。予約は推奨です。確実に買える・行列短縮・人数に合うサイズを選べるため、あなたにもお店にもプラス。ロス削減にもつながります。
- Q. いつなら当日でも大丈夫?
- A. 23・26日など混雑が弱い日、夜の値引き狙い、冷凍/カップ系で代替できる場合、地元の混雑が少ない店なら当日でもOKなことがあります。
- Q. 予約のコツは?
- A. 人数×1カットで必要量→受取枠を分散(23〜26日)→キャンセル規定と受取時間を必ず確認。迷ったらハーフ/カップで“食べ切り設計”。
- Q. クリスマスケーキはいつまで食べても大丈夫?
- A. 生クリームやフルーツを使ったホールケーキは、冷蔵でも翌日までを目安に食べ切るのが基本です。食べ切れない量は、1カットずつラップ&保存袋で冷凍し、1〜2週間以内に消費すると安心です。
- Q. 冷凍したケーキがパサパサになってしまいます。
- A. 空気に触れたまま冷凍するとパサつきやすいため、1カットずつラップで密着させ、さらに保存袋で二重に包むのがおすすめです。解凍は室温ではなく冷蔵庫で6〜8時間かけて行うと、食感の劣化を抑えられます。